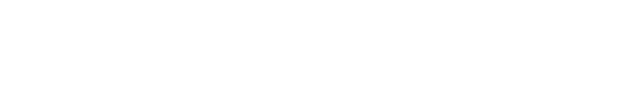非結核性抗酸菌症
非結核性抗酸菌症は、私が千葉で勤務してから、この地域に非常に多い感染症であることを実感しました。特に中高年の女性で長く続く咳嗽がある方、胸部異常陰影を認めた方では、一度同疾患の存在を疑うべきです。
どのような病気か
非結核性抗酸菌(nontuberculosy mycobacteriosis: NTM)は、結核菌以外の培養可能な環境に常在する抗酸菌を指します。
NTMは180種類以上あるとされておりますが、その中でも Mycobacterium avium complex (MAC)菌による肺MAC症が約90%を占めます。自然界の水回り・土壌などに常在し、人への曝露は頻回に起こっていると推測されています。
NTM症は結核とは異なり、人から人への感染は起こしません。数年から数十年の経過でゆっくり進行し、基本的に予後の良い病気です。ただし、時に慢性の咳・血痰などの症状を起こしたり、症状の進行に伴って呼吸不全を起こしたりすることもあります。
どのように診断を行うか
NTM症を疑ったときに行うべきは、まずは画像(レントゲンとCT)です。NTM症の画像は、大別して「小結節・気管支拡張型」と「線維空洞型」の2つの病型があります。
- CT画像(結節・気管支拡張型)
- CT画像(線維空洞型)
画像で非結核性抗酸菌症が疑われる場合、喀痰の検査(一般細菌と抗酸菌の両方)を行います。ただし、痰がどうしても出ないという方もいます。その場合、誘発喀痰(食塩水をネブライザーで吸入してもらい、痰を喀出して頂く)を行います。それでも痰がでない方は、胃液検査(食事を抜いた状況で、鼻からチューブを入れて胃液を採取して胃液の抗酸菌検査を行う)、さらには気管支鏡検査を考慮します。気管支鏡検査は、口からファイバーを挿入し、病変部に生理食塩水を注入し吸引・回収します。この気管支洗浄液で抗酸菌検査を行います。侵襲的な検査ですが、診断をしっかりつけたい方、特に免疫抑制剤や生物学的製剤の使用を考慮している方には、この気管支鏡検査を考慮します。
(当院では気管支鏡検査を実施しておりませんので、適宜、日本医科大学千葉北総病院にご紹介いたします)
喀痰検査で2回同じ菌が証明されたとき(気管支鏡検査では1回で可)、非結核性抗酸菌症(NTM症)との診断に至ります。
どのように治療を行うか
NTM症は結核と比較して一般に薬物療法が効きにくく、治療期間が長期にわたり、また治療終了後の再発も多いとされています。診断=即治療開始、ということではありません。ご本人の身体状態、年齢、併存症、排菌量、肺病変の広がり、そしてご本人の希望を踏まえて治療開始を検討します。
薬剤による治療の場合、クラリスロマイシンをキードラッグとして下記の表のような薬剤を3~4種類用いる多剤併用療法を行います。
| M.avium complex |
薬剤数 | 推奨レジメン | 投与頻度 |
|---|---|---|---|
| 結節・気管支拡張型 | 3 | ・アジスロマイシン(クラリスロマイシン) ・リファンピシン(リファブチン) ・エタンブトール |
週3回 |
| 空洞型 | ≧3 | ・アジスロマイシン(クラリスロマイシン) ・リファンピシン(リファブチン) ・エタンブトール ・アミカシン静注(ストレプトマイシン) |
毎日 ※ |
| 治療抵抗性 | ≧4 | ・アジスロマイシン(クラリスロマイシン) ・リファンピシン(リファブチン) ・エタンブトール ・アミカシンリボソーム吸入懸濁液 あるいは アミカシン静注(ストレプトマイシン) |
毎日 ※ |
※アミノグリコシドは週3回でよいかもしれない
ただし、多くの薬を飲むに場合には、副作用に注意が必要ですし、また他に飲んでいる薬に影響(相互作用といいます)しないか、確認しなければなりません。主な副作用について下記に示します。
| 治療薬(一般名) | 主な副作用 | |
|---|---|---|
| 内服薬 | リファンピシン | 肝機能障害、皮疹、食欲不振、白血球・血小板減少 |
| エタンブトール | 肝機能障害、皮疹、視神経障害 | |
| クラリスロマイシン | 下痢、腹痛など消化器症状、皮疹、QT延長 | |
| アジスロマイシン | 下痢、腹痛など消化器症状、皮疹、QT延長 | |
| 注射剤 | アミカシン | 皮疹、耳鳴、難聴、肝機能障害 |
内服期間に決められたものとして,喀痰検査で「菌が認められなくなってから(菌陰性化後)1年後まで」という一つの目安がありますが、絶対的ではありません。最近では、治療期間が菌陰性化後15か月未満の場合、また治療終了後に空洞がある場合は、再発のリスクとする報告もあり、内服の中止には注意が必要です。
排菌が停止しない若年例や空洞性病変が存在する例では、主病巣の外科的切除も考慮されます。
一方、色々と病気を抱えている場合、年齢が高い場合、軽症の場合は、無治療で経過をみていくことも選択肢となります。
当クリニックでどのように外来通院して頂くか
診断後、治療介入するかどうか検討します。治療を行う場合、副作用の出現に注意を払い、眼科や耳鼻咽喉科と連携を取る必要があります。
その上で定期的に画像(レントゲン、時にCT)や喀痰検査で評価を行いつつ、通院して頂きます。